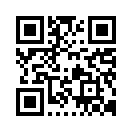2011年04月28日
村を守った二人のヒーロー・・・!?
必ず夜明けはやってくる!
そう信じ、心をひとつにして前を向いて頑張ろう!
本字湯のアケイディアの写真は公園です!

(画像をクリックすると拡大されます)




写真を見る限り、菜の花も咲いていて春真っ盛りって感じですね。
天気もよさそうで、さしずめ、「ぽかぽか日曜日」という感じですかね・・・!?(^_^)v
さて、表題の件ですが、昨日は「先人たちの教え」という題でブログを書かせていただきましたが、本日は、村を守った二人のヒーローについて書きたいと思います!
昨日のMSN産経ニュースに、死者ゼロの岩手・普代村を守ったのは… 2人の「ヒーロー」という記事タイトルを見つけました!
記事によると、過去の津波で多数の犠牲者を出した岩手県普代村は、今回の東日本大震災では死者ゼロ、行方不明者1人にとどまったそうです。\(◎o◎)/!
被害を食い止めたのは高さ15・5メートルもの水門と防潮堤だったそうです。
昭和40~50年代、当時の村長が反対の声を押し切り、建設にこぎつけたものだそうだが、ただ、今回は水門脇ゲートの自動開閉装置が故障し、1人の消防士が水門へ向かい、手動でゲートを閉めたのだそうです。
危機を見越した過去の政治的英断、そして地震直後の献身的な行動が村を守ったのだそうです。
久慈消防署普代分署の副分署長を務める立臼勝さん(50)は「水門の高さがもう少し低かったら、村にはすごい被害が出ただろう。もちろん私の命もなかった」と振り返ったそうです。
3月11日の地震直後、自動開閉装置の故障を知った立臼さんは、村を流れる普代川の河口から約600メートル上流にある水門に向かって消防車を走らせたとのこと。故障したゲートを閉めるには水門上部の機械室で手動スイッチを使うしかないからだったそうで、津波の危機感はあったが、「まさか、あれほど大きな津波がくるとは思っていなかった」とのこと。

機械室に駆け上がって手動スイッチに切り替えると鉄製ゲートが動き、ほっと一息ついて、消防車に乗って避難しようとしたとき、背後から「バキ、バキッ」と異様な音がするのに気付いたという。普代川を逆流してきた津波が黒い塊になって防潮林をなぎ倒し、水門に押し寄せてくる音だった。アクセルを踏み込み、かろうじて難を逃れたそうです。
津波は高さ20メートルを超えていたそうで、水門に激突して乗り越えたが勢いはそがれたそうです。水門から普代川上流にさかのぼってほどなく止まり、近くの小学校や集落には浸水被害はなかったとのこと。
立臼さんは「高い水門をつくってくれた和村さんのおかげ」と話したそうです。
和村さんとは、昭和22年から10期40年にわたり普代村の村長を務めた故・和村幸得さんのことだそうで、昭和8年の三陸大津波を経験し、防災対策に力を入れた村長だったそうです。
村では明治29年の大津波で302人、昭和8年の大津波でも137人の犠牲者を出した歴史があり、和村さんは「悲劇を繰り返してはならない」と防潮堤と水門の建設計画を進めたのだそうです。
昭和43年、漁港と集落の間に防潮堤を、59年には普代川に水門を完成させたそうです。
2つの工事の総工費は約36億円だったそうで、人口約3千人の村には巨額の出費で、建設前には「高さを抑えよう」という意見もあったそうです。だが、和村さんは15・5メートルという高さにこだわったとのこと。
普代村住民課長の三船雄三さんは「明治の大津波の高さが15メートルだったと村で言い伝えられていた。高さ15メートルの波がくれば、根こそぎやられるという危機感があったのだろう」と話し、和村さんは反対する県や村議を粘り強く説得し、建設にこぎつけたのだそうです。
村長退任時のあいさつで職員に対し「確信を持って始めた仕事は反対があっても説得してやり遂げてください」と語ったという和村さんだったそうですが、三船さんは「当時の判断が村民の命を守ってくれた、とみんな感謝している」と話していたそうです。

昨日の「先人の知恵」同様、すばらしい村長さんと消防士さんのおかげで、まさしく村が守られたのでしょう。\(^o^)/
このようなすばらしい方々のエピソードはこれからもたくさん耳にすることと思いますが、我々大震災に遭わなかった人も、自分なりにお役立ちできることで、少しでもいいから貢献できたらいいなと思います。

今日という一日にありがとう。
今日の出会いにありがとう。
そしてあなたにありがとう。
そう信じ、心をひとつにして前を向いて頑張ろう!
本字湯のアケイディアの写真は公園です!


(画像をクリックすると拡大されます)




写真を見る限り、菜の花も咲いていて春真っ盛りって感じですね。
天気もよさそうで、さしずめ、「ぽかぽか日曜日」という感じですかね・・・!?(^_^)v
さて、表題の件ですが、昨日は「先人たちの教え」という題でブログを書かせていただきましたが、本日は、村を守った二人のヒーローについて書きたいと思います!

昨日のMSN産経ニュースに、死者ゼロの岩手・普代村を守ったのは… 2人の「ヒーロー」という記事タイトルを見つけました!

記事によると、過去の津波で多数の犠牲者を出した岩手県普代村は、今回の東日本大震災では死者ゼロ、行方不明者1人にとどまったそうです。\(◎o◎)/!
被害を食い止めたのは高さ15・5メートルもの水門と防潮堤だったそうです。

昭和40~50年代、当時の村長が反対の声を押し切り、建設にこぎつけたものだそうだが、ただ、今回は水門脇ゲートの自動開閉装置が故障し、1人の消防士が水門へ向かい、手動でゲートを閉めたのだそうです。

危機を見越した過去の政治的英断、そして地震直後の献身的な行動が村を守ったのだそうです。

久慈消防署普代分署の副分署長を務める立臼勝さん(50)は「水門の高さがもう少し低かったら、村にはすごい被害が出ただろう。もちろん私の命もなかった」と振り返ったそうです。

3月11日の地震直後、自動開閉装置の故障を知った立臼さんは、村を流れる普代川の河口から約600メートル上流にある水門に向かって消防車を走らせたとのこと。故障したゲートを閉めるには水門上部の機械室で手動スイッチを使うしかないからだったそうで、津波の危機感はあったが、「まさか、あれほど大きな津波がくるとは思っていなかった」とのこと。


機械室に駆け上がって手動スイッチに切り替えると鉄製ゲートが動き、ほっと一息ついて、消防車に乗って避難しようとしたとき、背後から「バキ、バキッ」と異様な音がするのに気付いたという。普代川を逆流してきた津波が黒い塊になって防潮林をなぎ倒し、水門に押し寄せてくる音だった。アクセルを踏み込み、かろうじて難を逃れたそうです。

津波は高さ20メートルを超えていたそうで、水門に激突して乗り越えたが勢いはそがれたそうです。水門から普代川上流にさかのぼってほどなく止まり、近くの小学校や集落には浸水被害はなかったとのこと。

立臼さんは「高い水門をつくってくれた和村さんのおかげ」と話したそうです。

和村さんとは、昭和22年から10期40年にわたり普代村の村長を務めた故・和村幸得さんのことだそうで、昭和8年の三陸大津波を経験し、防災対策に力を入れた村長だったそうです。

村では明治29年の大津波で302人、昭和8年の大津波でも137人の犠牲者を出した歴史があり、和村さんは「悲劇を繰り返してはならない」と防潮堤と水門の建設計画を進めたのだそうです。

昭和43年、漁港と集落の間に防潮堤を、59年には普代川に水門を完成させたそうです。

2つの工事の総工費は約36億円だったそうで、人口約3千人の村には巨額の出費で、建設前には「高さを抑えよう」という意見もあったそうです。だが、和村さんは15・5メートルという高さにこだわったとのこと。

普代村住民課長の三船雄三さんは「明治の大津波の高さが15メートルだったと村で言い伝えられていた。高さ15メートルの波がくれば、根こそぎやられるという危機感があったのだろう」と話し、和村さんは反対する県や村議を粘り強く説得し、建設にこぎつけたのだそうです。

村長退任時のあいさつで職員に対し「確信を持って始めた仕事は反対があっても説得してやり遂げてください」と語ったという和村さんだったそうですが、三船さんは「当時の判断が村民の命を守ってくれた、とみんな感謝している」と話していたそうです。


昨日の「先人の知恵」同様、すばらしい村長さんと消防士さんのおかげで、まさしく村が守られたのでしょう。\(^o^)/
このようなすばらしい方々のエピソードはこれからもたくさん耳にすることと思いますが、我々大震災に遭わなかった人も、自分なりにお役立ちできることで、少しでもいいから貢献できたらいいなと思います。


今日という一日にありがとう。
今日の出会いにありがとう。
そしてあなたにありがとう。
Posted by アケイディアと陽彩のじーじー at 18:41│Comments(0)
│じーじーのお気に入り
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。